-
白ワインおすすめワイン
もっと知りたいワイン マロラクティック発酵とシュール・リー【2020】
マロラクティック発酵やシュール・リーによってワインの性格が変わる!

-
Stay Home期間中にじっくりゆっくりワインを楽しむ時間が増えたことで、もう少しワインについて知りたくなった、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
白ワインの醸造用語で度々耳にする「マロラクティック発酵(M.L.F.)」と「シュール・リー」。この二つの醸造方法はどんな製法で、これらによってワインにどんな変化が起こるのかを知ると、白ワインの香りや味わいの違いが分かりやすくなります。
「マロラクティック発酵」は、ワインに含まれるリンゴ酸が乳酸菌の働きによって、乳酸と二酸化炭素に変化することです。この説明だけでは、ワイン醸造の化学的過程のひとつでしかないように聞こえますが、ワインの味わいにおいてとても大切な酸を変化させるので、マロラクティック発酵の有無によって、ワインの味わいが大きく異なります。
赤ワインの醸造過程では、マロラクティック発酵がほぼ行われますが、白ワインを醸造する場合、すっきりした味わい、もしくは、まろやかな味わい、どちらを望むかによって、マロラクティック発酵を取り入れるかが決まります。
ワインの原料となるブドウに含まれる主要な酸は、酒石酸とリンゴ酸です。ブドウに多く含まれる酒石酸ですが、この有機酸を含む果実は少ないそうです。
酒石酸はワインになった後もそのまま残り、コルクの裏側に付着した、または、ビン底に溜まったキラキラした結晶を目にしたことがあると思いますが、その結晶が、酒石酸がカルシウムと結合したものです。
もう一つの有機酸であるリンゴ酸は、まさに青りんごを齧ったようなフルーティですっきりとした酸味です。涼しい産地で育ったブドウに多く含まれ、暖かい産地では少なくなりますので、醸造方法によっても変わりますが、基本的には涼しい産地のワインのほうがスッキリした味わいになるのはこのためです。
マロラクティック発酵を行うと、このシャキッとしたリンゴ酸が和らいで、まろやかな乳酸に変わり、更に、副産物として、バターやナッツの風味と表現されるジアセチル(ダイアセチル)が生成されることで、ワインによりまろやかな印象を与えるのです。
次に、「シュール・リー」とはどのような製法なのでしょうか。
フランス語を直訳すると、「シュール(Sur)=上」、「リー(Lie)=澱・オリ」、すなわち「澱の上」という意味です。一般的な白ワインは、発酵が終わると、発酵槽の底に沈殿した澱(酵母の死骸等)を取り除く「澱引き」をします。しかし、澱とともにワインを数か月間熟成させることで、澱由来の風味や旨味をワインに取り込ませ、ワインに深みを与える手法がシュール・リーです。フランス・ロワール地方のミュスカデや、日本の甲州に使われる手法として知られていますが、赤ワインで試みる生産者もいるそうです。
今回は、マロラクティック発酵を取り入れて造られたワインと、シュール・リー製法を行って仕上げたワインをご紹介いたします。
ちょうど、冷えた白ワインがおいしい季節。実際にワインを飲みながら、製法による個性の違いを探してみるのはいかがでしょうか。
-
-

-

フランス ブルゴーニュ
ファミーユ・マッス
ジヴリ ル・クロ・ド・ラ・ロッシュ 白
スーペリアクラス

白
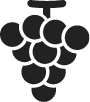
スティルワイン
-
-
<60%をオーク樽、40%をステンレス・タンクにて主発酵後、マロラクティック発酵> 高品質であり低価格であることにこだわったワイン造りを貫く生産者。南仏の豊かな気候で育ったブドウならではの果実味とコクが楽しめます。
-

-

フランス ラングドック&ルーシヨン
ドメーヌ・ポール・マス
アロガント・フロッグ シャルドネ
カジュアルクラス

白
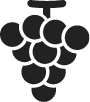
スティルワイン
-
-
<ステンレスタンクにて発酵、マロラクティック発酵なし> 2つめにご紹介したワインと同じ生産者がマロラクティック発酵なしで造るワイン。ブドウ品種は異なりますが、2つめのワインと同じタイプの土壌で育ったブドウで造られています。マロラクティック発酵の有無による違いを探してみるのはいかがでしょうか。
-

-

フランス ラングドック&ルーシヨン
ドメーヌ・ポール・マス
コーテ・マス ミュスカ・セック
デイリークラス

白
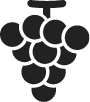
スティルワイン
-
-
ミュスカデ地区でも最上級クラスのブドウ畑を所有し、ミュスカデ最高の造り手と謳われる生産者。ランドロン家がこだわるシュール・リー製法によって、ドメーヌが誇る複雑で個性的なテロワールを存分に発揮したワインを生み出します。
-

-

フランス ロワール
ドメーヌ・ランドロン
ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ シュール・リー ラ・ルヴトゥリ
カジュアルクラス

白
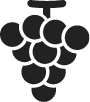
スティルワイン
-
-
甲州に特化し、勝沼のテロワールを追究する造り手として日本国内のみならず世界的にも高い注目を集めている生産者。丁寧に時間をかけてゆっくりと搾った甲州の果汁をシュール・リー製法で仕上げます。
-

-

日本 山梨県
勝沼醸造株式会社
甲州テロワール・セレクション 祝
カジュアルクラス

白
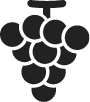
スティルワイン
-
口コミ
もっと見る
- 公開日 :
- 2020/08/03
- 更新日 :
- 2020/08/04







<主発酵後、オーク樽にてマロラクティック発酵> 4代目となる現当主より評価が急上昇中のドメーヌ。彼が造るワインは果実味重視でやわらかなタイプ。除梗を100%行い、ピジャージュはせずに醸造されます。